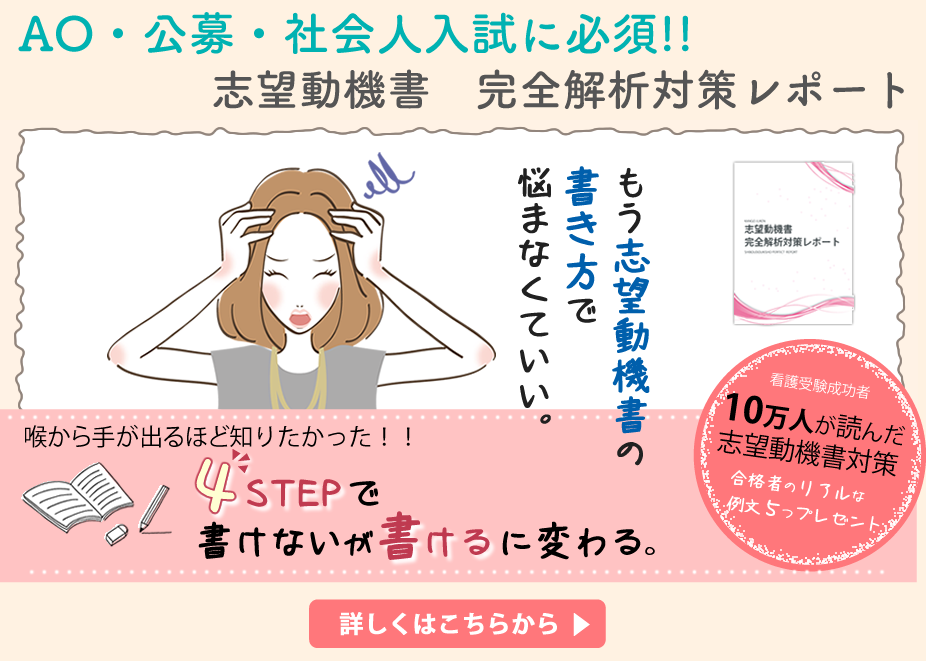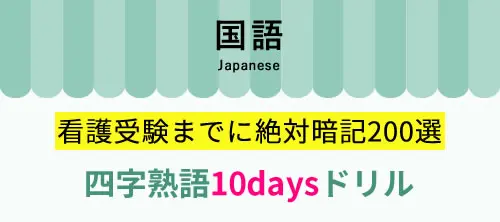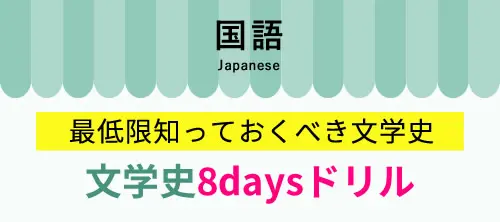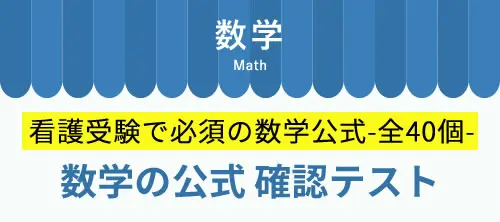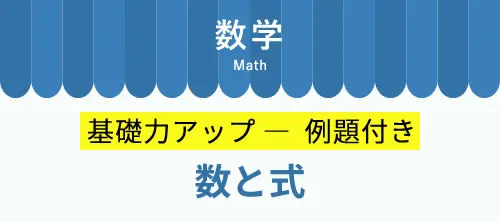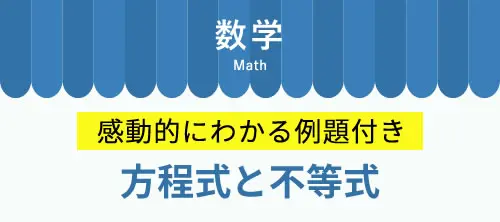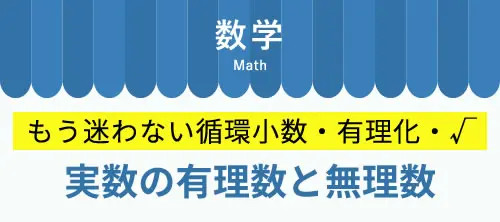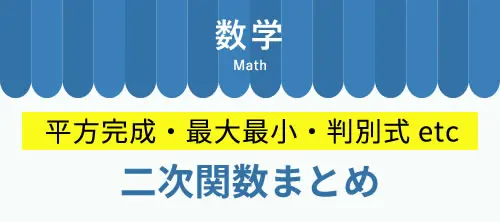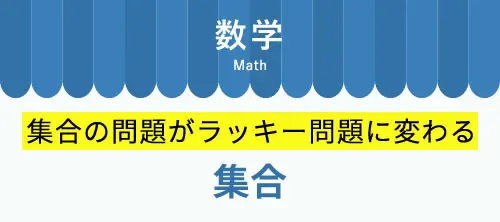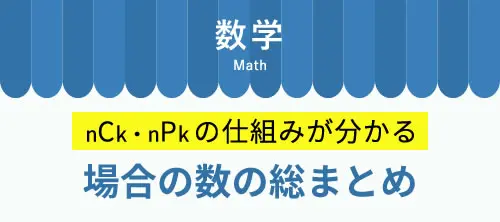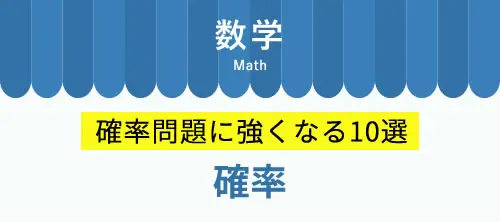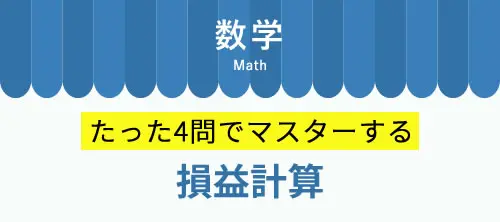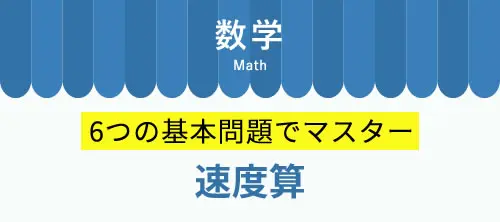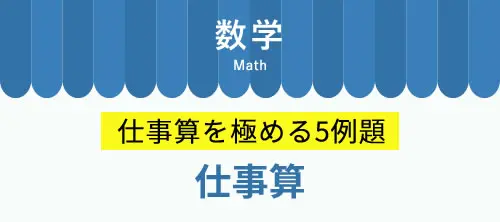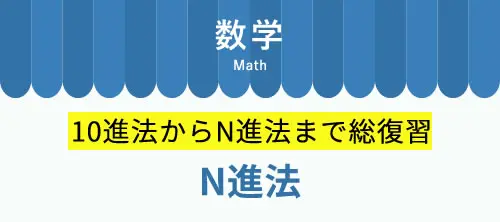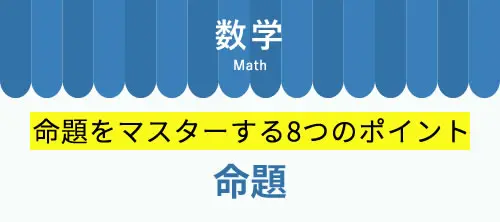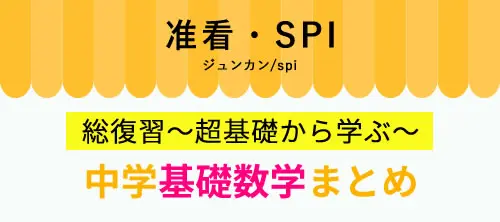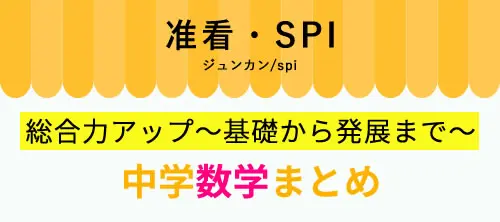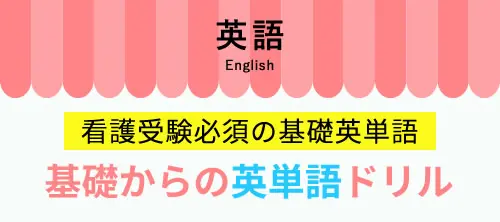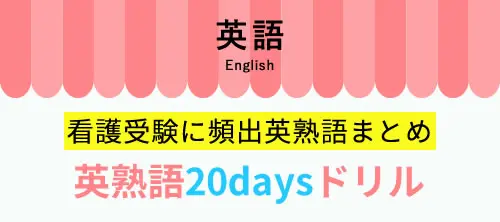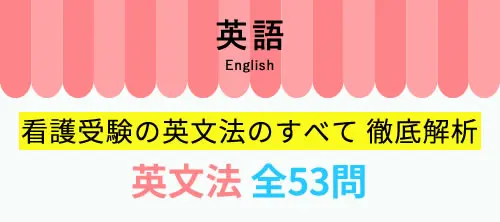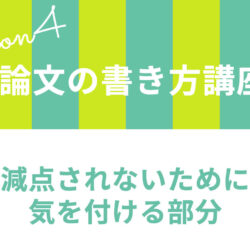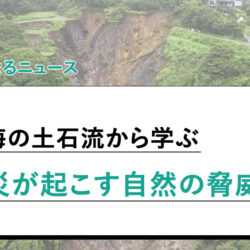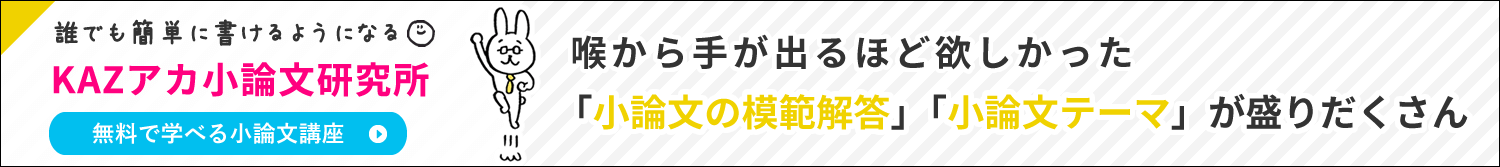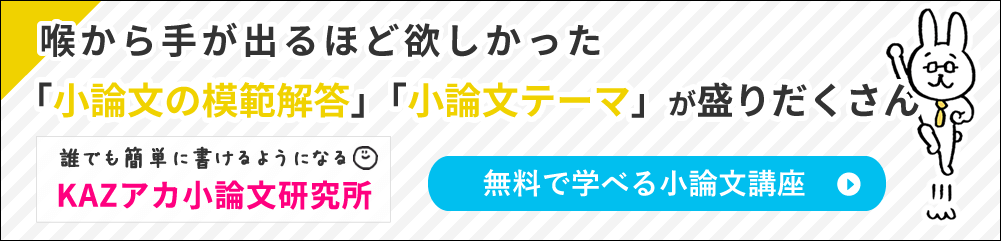湿気と日本文化 設問別・要点解説
全体の流れ(まずここを押さえる)
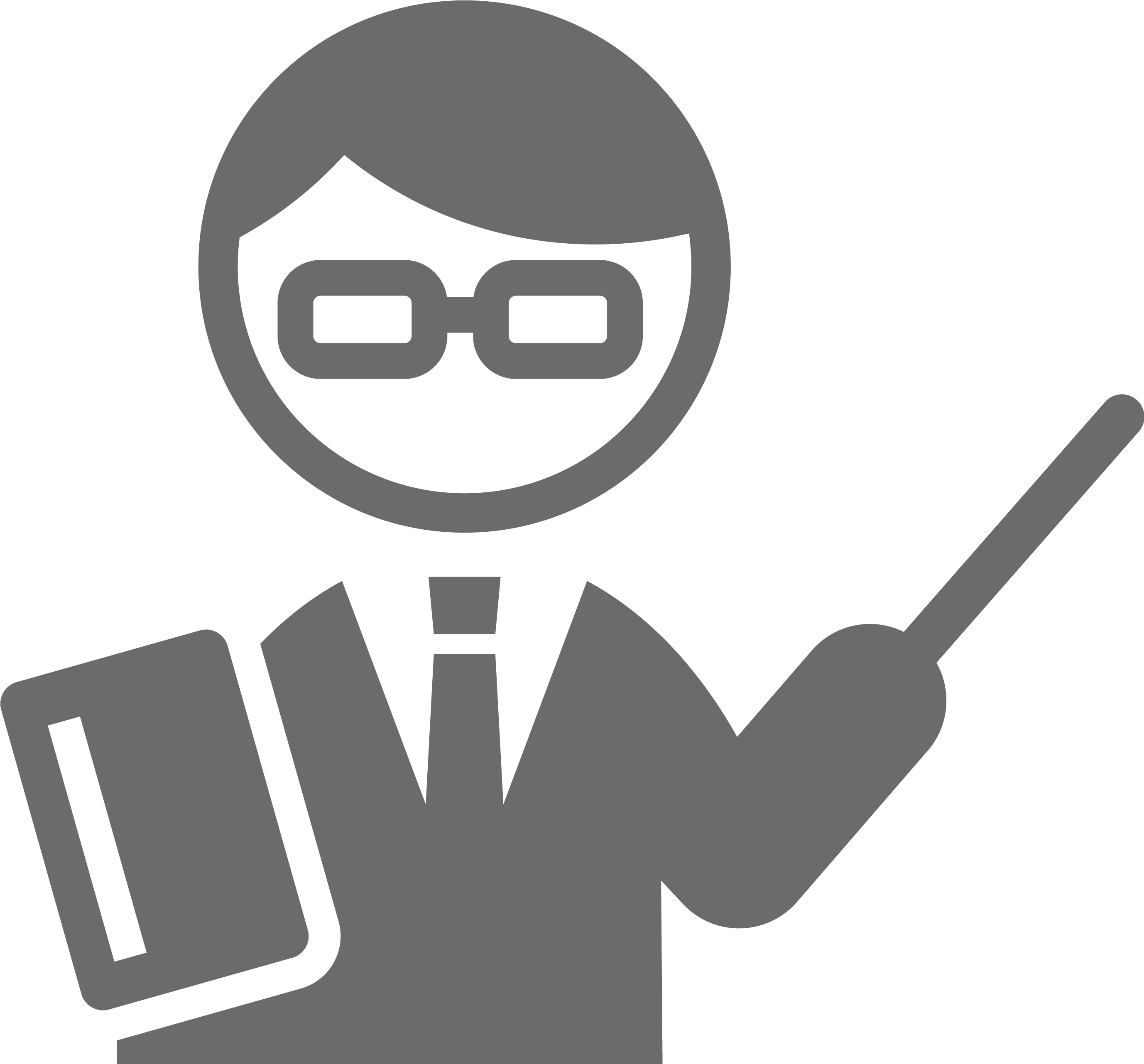
・①段落=総説。日本は「湿気の国」で、その湿気が衣食住や作法・感性を形づけてきたと述べます。
・②段落=具体例①「打ち水」。日本は湿りを歓迎とみなし、欧米はまず乾かすという対比で主張を説明します。
・③段落=具体例②「苔寺」。苔を美として受け取る日本と、汚れ・荒廃とみなす欧米を対比し、自然観の違いにまとめます。
・結び=日本は自然と〈融和〉、欧米は自然と〈闘争〉という見方の差が感性の差を生む、という整理です。
1⃣ 問題(1)
【②段落と①段落の関係】
第2段落は、第1段落の「日本は湿気の国で、その気候が作法や感性を形づくった」という主旨を、来客時の「打ち水」と欧米との対比という具体例で説明しているため。
解答 → イ
問題(2)
【②段落の例から一般化した筆者の言いたいこと(32字)】
・該当は「日本人は……生きている」という趣旨の一文です。
初めの四字 → 日本人は / 終わりの四字 → きている
問題(3)
【③段落の中心文(初めの五字)】
・中心文 = 例を受けて日本側の主張を一般化した文の冒頭です。
解答 → 苔寺のよさ
問題(4)
【段落どうしの関係図】
②段落:具体例①(打ち水)+欧米との対比。
③段落:具体例②(苔寺)を示したうえで、末尾で「自然と闘う欧米/自然と融和する日本」という本文全体の総括を述べる。
→ つまり、①と②で示した内容を受けて③でまとめる
解答 → イ
他の選択肢が違う理由
ウ:①が主張で②・③が並列の具体例、という図。しかし③は結論を出しているので単なる並列例示ではない。
ア:1→2→3の直列展開ではない(②と③は同格の材料)。
エ:②・③を受けて①が結論という図だが、①は冒頭の総説であって結論ではない。